【重要度:★★★★☆…直接何かが変わったわけではないけど、今の“世界の空気感”がにじみ出た出来事。AIや中東支援では足並みがそろった一方、ウクライナ支援や自動車関税などでは溝が表面化。ふだんニュースを見ない人にとっても、「世界がどこへ向かうか」を考えるきっかけになるような内容だった】

最近、「G7サミットが開かれました」ってニュース、なんとなく見かけませんでしたか?
なんかスーツ姿のえらい人たちが集まって、世界のことを話し合ってるっぽいけど、正直、何を決めてるのか、私たちにどう関係あるのかって…よくわからない。
でも今年(2025年)のG7は、ちょっと空気が違いました。
ニュースでは「AI」や「中東」みたいな話が報じられた一方で、日本や世界の未来に関わる話が、あまり前に進まなかったんです。
たとえば──
- ロシアと戦ってるウクライナへの支援。今回は“支援します”という声明すら出せず。
- 日本がお願いしてたアメリカの“自動車への関税”も、結局そのまま。
- そして、アメリカのトランプ大統領は、途中でサミットを抜けて帰ってしまった。
「え、そんなことでいいの…?」と思うかもしれません。
でも実はこうした“進まなかった話”こそが、これからの国際関係や、私たちの生活にじわじわ効いてくるかもしれないんです。
この記事では、G7って結局どんな会議なのか、何が話題でどんな影響が出るのか、やさしく整理していきます。
G7ってそもそも何?
そもそも「G7」って、何なんでしょう?
ニュースでよく聞くけど、なんとなく「世界の偉い国たちが集まって、何か決めてる会議」くらいのイメージかもしれません。
正式には「先進7カ国首脳会議(Group of Seven)」といって、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、そして日本の7つの国がメンバーです。
これに加えて、欧州連合(EU)も「毎回よく呼ばれる常連ゲスト」みたいな感じで参加しています。
このG7サミット、開催は年に1回で、メンバー7カ国が持ち回りでホスト(開催国)を担当しています。
つまり、その年のホスト国が「今年はこれについて話そう」「この国も招待してみよう」といった、会議のテーマや雰囲気をある程度コントロールできます。
ちなみに2025年はカナダがホスト。
前回の2024年はイタリア、その前の2023年は日本(広島)で開かれました。
決める力は“強くない”。でも、注目される
G7のちょっとややこしいところは、「何かを決める場」ではないという点です。
たとえば、国連では「これやりましょう」と決めれば、加盟国に義務が生じたりします。
でもG7はそうじゃなくて、あくまで“話し合って、方向性をすり合わせて、メッセージを出す”会議です。
「なんだ、決まらないのか」と思うかもしれませんが、だからこそ、各国の“本音”や“今どっちを向いてるか”が見えるという意味で、世界から注目されているんです。
「みんなで同じ方向を見てるよ」ってことが重要
たとえば、過去にはこういうメッセージが出されました:
- 「コロナにどう対応するか、世界で協力しよう」
- 「ロシアのウクライナ侵攻は許せない。支援を続けるべきだ」
- 「AIや気候変動、ルールがまだ整ってない問題にも先進国として向き合おう」
こういうのって、強制力はないけど、「世界の“スタンダード”になるきっかけ」になるんです。
だから、逆に言えば、G7で“意見がそろわなかった”ときは、それ自体がニュースになる。
「世界が一つになれない」ことが、はっきり見えてしまうからです。
つまり、G7は「未来の空気感」が見えてくる会議
G7は、目に見える政策や法律を作る場所じゃないけど、ここで話し合われるテーマ、そこに表れる温度差は、やがて私たちの仕事、暮らし、物価、テクノロジーにじわじわ効いてくるもの。
だからこそ、「どの国がどんなことを大事にしてるのか」を知る場として、実はめちゃくちゃ大事なんです。
2025年のG7で何が起きた?
2025年のG7サミットは、6月16日と17日の2日間、カナダの山あいにあるリゾート地「カナナスキス」で開かれました。
今回のホスト国はカナダ。各国のリーダーたちが集まり、経済・安全保障・技術など、世界の大きな課題について話し合いました。
各国で合意できたこと
今回のG7で、「これは一緒に取り組もう」と合意されたのは、こんな内容です。
▶ AI・量子技術など、最先端分野での協力
AI(人工知能)や量子コンピューターといった、次の時代の技術について、先進国どうしでルールづくりや人材育成などを一緒に進めていこうというものです。
- 世界で技術開発の“主導権”を握るには、国ごとのバラバラ対応では限界がある
- G7として足並みをそろえることで、中国などへのけん制にもつながる
▶ 重要鉱物のサプライチェーン強化
電気自動車(EV)やスマホのバッテリーなどに必要なレアメタル(希少な鉱物)。
これまでは中国に頼る部分が大きかったため、調達先を分散しようという方針で一致しました。
- 「資源をめぐる争奪戦」に巻き込まれないための準備
- 安定した供給体制を整えることで、価格や技術のコントロール力を確保
▶ 中東への対応:イランとイスラエルの問題
中東では、イランとイスラエルの緊張が高まっています。
G7としては、「イランの核保有は認めない」という立場をあらためて明言し、イスラエル防衛への支持を示すことで一致しました。
こうした内容は、「G7として世界に発信する“共通の立場”」として、今後の国際ルールや交渉の前提になっていきます。
逆に、まとまらなかったこともあった
でも今回のG7では、実は“話し合えなかったこと”にこそ注目が集まりました。
▶ ウクライナ支援の共同声明、出せず
ロシアの侵攻が続くウクライナへの支援は、これまでG7が最も足並みをそろえてきた分野でした。
ところが今回は、アメリカのトランプ大統領が「支援に慎重な姿勢」を見せ、なんと途中でサミットを退席。
その影響もあり、ウクライナ支援に関する共同声明は出されませんでした。
G7が“支援の意思を示せなかった”という事実は、国際社会への影響が小さくない出来事です。
▶ 日本が求めた「自動車関税の撤廃」も進展なし
もうひとつ、日本にとって大事なテーマだったのが、アメリカが日本車にかけている25%の関税問題。
日本側は「関税をなくしてほしい」と求めていましたが、結局、交渉は平行線。「今後も話し合いましょう」という曖昧な結果に終わりました。
トランプ政権は「アメリカ第一」の方針を取っており、こうした貿易交渉も難航しがち。
日本の“主力産業”である自動車分野にとっては、不安の残る展開です。
「決まったこと」と「決まらなかったこと」──その差が見せる“今の世界”
今回のG7は、たしかにいくつかの分野では合意できました。
でも一方で、「本来なら一致できていたはずのテーマ」で足並みが揃わなかったことも事実です。
その背景には、各国が重視しているものが違いはじめているという空気があります。
「世界がこれまでのようにはまとまらないかもしれない」──
そんな兆しが、今回のG7にはにじんでいました。
なぜ“決まらなかったこと”が気になるの?
普通、ニュースで注目されるのは「何が決まったか」ですよね。
でも今回のG7は、むしろ「決まらなかったこと」のほうに、今の世界の空気が出ていました。
たとえば──
- ウクライナ支援:これまでG7全体で支えてきたのに、今回はアメリカの姿勢でまとまらず。
- 自動車関税:日本が求めていた“25%関税の撤廃”も、何も動かなかった。
こういう「止まった話」って、一見つまらなく見えるかもしれません。
でも実は、「どこにズレがあるのか」「今、何に慎重になってるのか」が表れているポイントなんです。
そしてそのズレが、これからの経済や国際ルール、わたしたちの生活に、じわじわ響いてくる可能性がある。
だから今回のG7は、「何が決まったか」だけじゃなく、「何が決まらなかったか」にも、ちゃんと目を向ける必要があるんです。
これから何が起こる?わたしたちへの影響は?
ニュースで「G7が〜」って言われても、やっぱりどこか遠い話に感じてしまいますよね。
でも今回のG7サミットで“進まなかった話”を見ていくと、それが実は、わたしたちの給料や物価、将来の仕事にもつながってるかもしれないって話なんです。
クルマの関税、私たちに何の関係があるの?
アメリカは今、日本のクルマに最大25%の関税をかけています。
日本側は「それやめてよ」と言ってるけど、今回も進展はなし。
でもこれ、車業界だけの話じゃありません。
自動車って、日本にとっては“稼ぎ頭”なんです。
たくさん海外で売って、それが給料や雇用につながってる。
だから関税が続くと──
- メーカーの利益が減る
- ボーナスが出にくくなる
- 採用も減るかも
- 結果、円安が進んで物価が上がる
じわじわ効いてくる、ってこういうことかもしれません。
ウクライナ支援が止まると、ガソリン代が上がる?
今回は「ウクライナを支援しよう」という声明も出せませんでした。
もし支援が弱まって、ロシアが優位になれば──
原油や天然ガスの価格が不安定に。
ガソリン代が上がる、電気代も上がる。
それに備えて防衛費が増えて、税金の負担が増える
これ、ぜんぶ“遠い国の話”じゃなくて、普通に生活費の話なんです。
AIとかレアメタルの話って、自分に関係ある?
正直、「量子コンピューター」「鉱物のサプライチェーン」とか言われても、「いやもう、理科の授業ですか?」って感じかもしれません。
でもここ、10年後の「どこに仕事があるか」を左右する話なんです。
国が本気で育てる分野って、そこに人もお金も集まって、将来の“当たり前”を作っていく。
つまり「どんなスキルを持ってると強いか」も、こういう国際ルールや方針の積み重ねで決まってくるんです。
まとめ:G7は“未来をのぞき見る鏡”
G7サミットって、「今日からこれが変わります!」みたいな即効性のあるイベントじゃありません。
でも、各国が集まって、どんな話をして、どこで足並みが揃わなかったのか──
そこを見ていくと、これから世界がどう動いていくかのヒントが、少しずつ見えてきます。
今回のG7では、AIや鉱物など「未来の産業」をめぐる協力には、しっかり合意できた。
でも一方で、ウクライナ支援や自動車関税みたいな“今の暮らし”に近いテーマでは、足並みが揃わなかった。
「どこで協力できて、どこで止まったのか」
それが、いま世界が向かっている方向を表している気がします。
そして、その方向の先には──
- ガソリン代や電気代がどうなるか
- 就職先がどんな業界になるか
- 物価がどこまで上がるか、税金がどうなるか
そんな、わたしたちの未来に直結する話が続いているんですよね。
ニュースって、気づいたら「決まったこと」ばかり追ってるけど、実は「決まらなかったこと」のほうが、私たちの未来をじわじわ変えることもある。
G7もそのひとつ。
だからたまには、こんな視点でニュースを見てみてもいいのかもしれません。
「ジブンゴト+」でもっと深く
G7が世界の中心として大きな影響力を持っているのは間違いないけど、最近はその傾向に少しずつ変化ができてきてる。
インドやサウジアラビアといった次世代の有力国の集まりである「グローバルサウス」がどんどん力を強めてる。
経済的に見ても今の先進国は昔ほど大きな影響力は持っていなくて、GDPもどんどん「グローバルサウス」をはじめとした新興国の割合が大きくなってる。
しかも今世界が抱える地球温暖化とかの国際問題は先進国だけじゃなくてこれらの国の協力が必要不可欠。
だからこそG7の国々もこれらの国には一目置いた外交を行ってる。
今後の世界を占うといっていい「グローバルサウス」とはそもそも何なのか、深堀りしてみました。
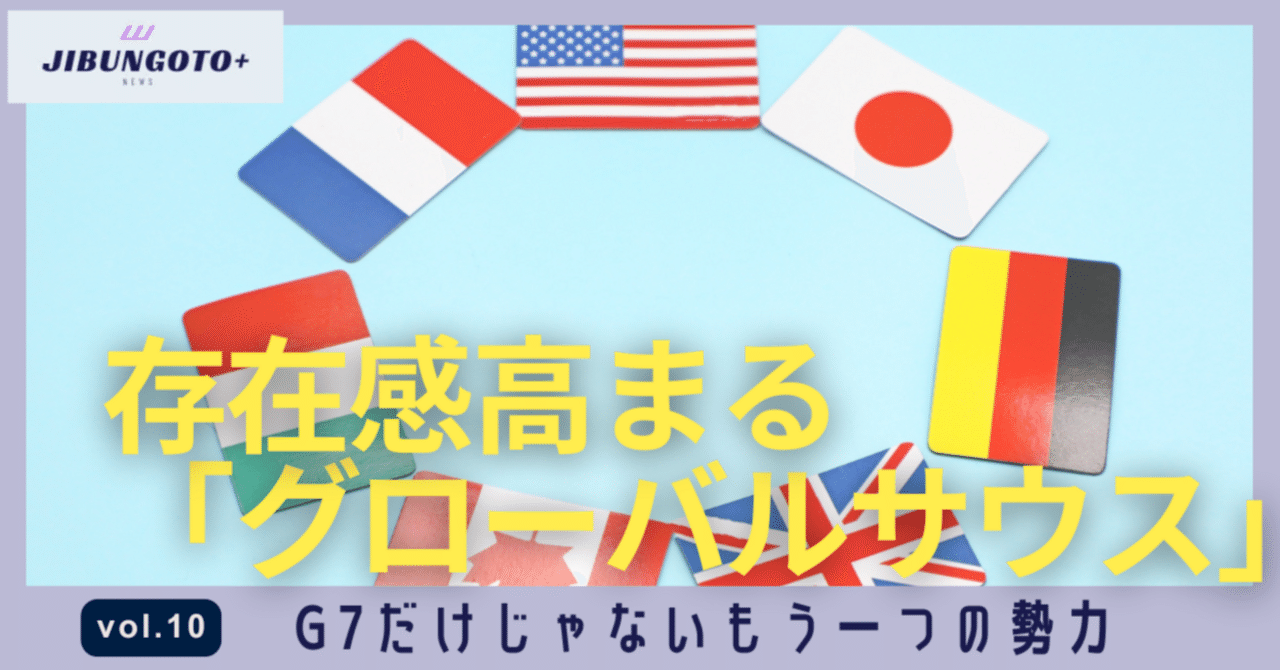




コメント